つくる
地域循環共生圏づくり支援体制構築事業
本事業では、各地域における地域循環共生圏づくりを強力に推進するため、各地域において、地域循環共生圏づくりに取り組む団体と、その団体への中間支援を行う主体を募集します。
過年度事業:環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業
実際に地域が主役となって地域プラットフォームをつくろうとしても、想いを持った個人が一人で取り組み始めるのは大変です。「地域循環共生圏創造の手引き」を読んで進め方は分かっても、実際にやってみると様々な壁にぶつかることもあるでしょう。本事業はそのような皆様を支援し、プラットフォームづくりを丁寧にサポートします。
- 話しを聞きに行く! - 協働の仲間づくり(ステークホルダーリスト作成)
- 地域のコンセプトを描く! - 計画づくり(地域版マンダラを描く)
- 事業のストーリーを語る! - ローカルSDGs事業を発想する(事業のタネづくり)
- みんなで目指す目標を立てる! - 成果指標を設定する(目標シートに取りまとめ)
- 事業主体(候補)を発掘する
- 事業主体が事業を起こすためのチャレンジをサポートする - 構想・計画のブラッシュアップ、試行、資金調達、マッチング等
- 地域プラットフォームの運営体制を強化する
地域循環共生圏に関するイベント
地域プラットフォームづくりに取り組むなかで、スキルアップしたい、他の地域の事例を聞いてみたい。そんな皆様のために、環境省は定期的にオンラインセミナーやフォーラムを開催しています。

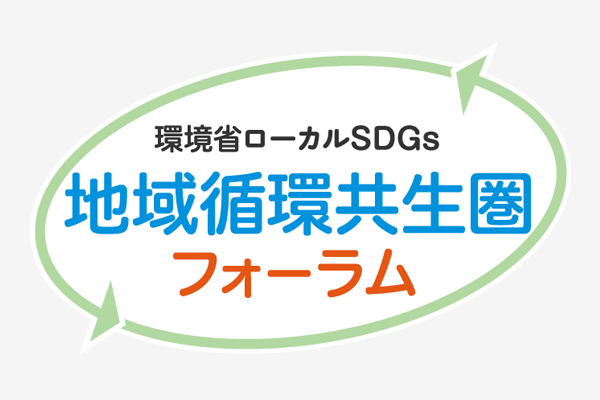
環境・社会・経済の同時解決で、好循環を生み出し、様々なステークホルダーを巻き込むヒントをご紹介します!
その他の地域循環共生圏づくりに活用できる事業
地域循環共生圏づくりに活用できる事業は他にもあります。
ここでは代表的な事業をご紹介します。

地域の脱炭素化は、脱炭素以外の地域課題と同時解決できる事業を、地域の人材が主体的に、様々な主体と協働して取り組むことが重要です。このため、地域循環共生圏の考え方で取り組むことが効果的です。

アドバイザーを派遣することで、当該地方公共団体の取り組みを支援し、地域脱炭素を加速することを目的とします。

本イベントは、これを解消する一助として、専門的な技術やノウハウを有する企業地方公共団体とのマッチングを行うことを目的として開催いたします。
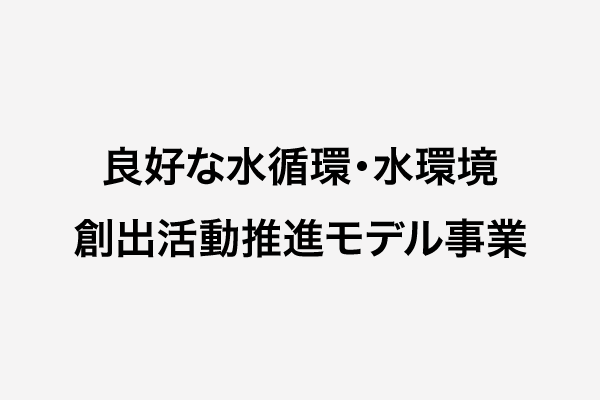
事業を通じて、地域の課題解決や取組の支援を行い、生物多様性保全や地域づくり等にも資する総合的な水環境管理の検討を行い優良事例の形成・普及を目指します。

本事業では、里海の拡大を図るため、藻場(もば)や干潟(ひがた)の保全・再生・創出と、藻場等における環境学習カリキュラムの開発や旅行会社と提携したエコツアーの造成といった取組を支援し、藻場等の保全・再生・創出と地域資源の利活用の好循環を生み出すことを目指します。

2~5名で1組のチーム単位で応募し、オンラインを基本としつつ現地フィールドワークも行い、現地事務局、講師陣による伴走のもと新たなプロジェクトを構想していきます。
地域循環共生圏づくりの相談窓口
「地域のみんなを巻き込みたい」
でもどんな人がいるんだろう、どう声掛けしたらいいんだろう。
そう思った時は、「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」や、「地方環境パートナーシップオフィス(EPO)」に相談してみましょう。
GEOCと全国8か所のEPOは、環境省と中間支援組織が共同で運営している、地域の特徴を活かした環境活動の活性化やパートナーシップ(協働)による地域づくりを推進する拠点です。
持続可能な地域づくり・地域循環共生圏づくりに関する相談にのったり、各種セミナー開催やプロジェクト伴走支援などを通じて、地域での人々のネットワーク拡大を応援しています。
※(at)は、@に置き換えてください。
地域循環共生圏のニュースを受け取る
地域循環共生圏に関連する情報を、メールマガジンやFacebook、noteにて配信しています。











